データサイエンス&先端技術
ロボット×テクノロジーで社会を守る:株式会社イクシス
2025.02.19

インタビュー者紹介
株式会社イクシス
代表取締役Co-CEO兼CTO (共同経営者)
山崎 文敬 氏Yamasaki Fuminori
企業や研究機関、自治体といった様々なパートナーと連携し、エネルギーや環境、次世代技術に関する課題解決や新しい価値創造を目指す、ENEOS CVC。今回紹介する企業は、2022年6月にENEOSが出資を行った、ロボット、AI、IoT、ICT機器及びソフトウェア等社会インフラに特化した、高付加価値の製品・サービスを提供する「株式会社イクシス」です。
ENEOSは国内外の製油所や化学プラントにおける設備の老朽化・新設に伴い、保守点検に係るコストや要員が増加している中で、イクシス社と共にロボティクスを活用した先進的な保守点検サービスについて様々な検討を進めています。
今回のインタビューでは、イクシス社が取り組む先端技術を用いた課題解決のプロセスや、ENEOSからの出資に至った経緯、そして目指すべき将来像などについて、代表取締役Co-CEO兼CTO (共同経営者)の山崎文敬氏に話を伺いました。
ロボット×テクノロジーでインフラの課題を解決
―まずはイクシス社の概要について教えてください。
弊社は、私が大学院生の時に起業した会社です。学生の頃からロボット作りに没頭していて、当初は人型ロボットなどを制作していたのですが、せっかく作るなら専門的な領域で活躍できる役立つロボットを世に出したいと思い、インフラに特化したロボットの開発を始めました。
今年で創業27年目。現在ではインフラ業界でロボットを作る会社といえば弊社の名前がすぐに挙がるほど、かなり認知していただいていると自負しています。
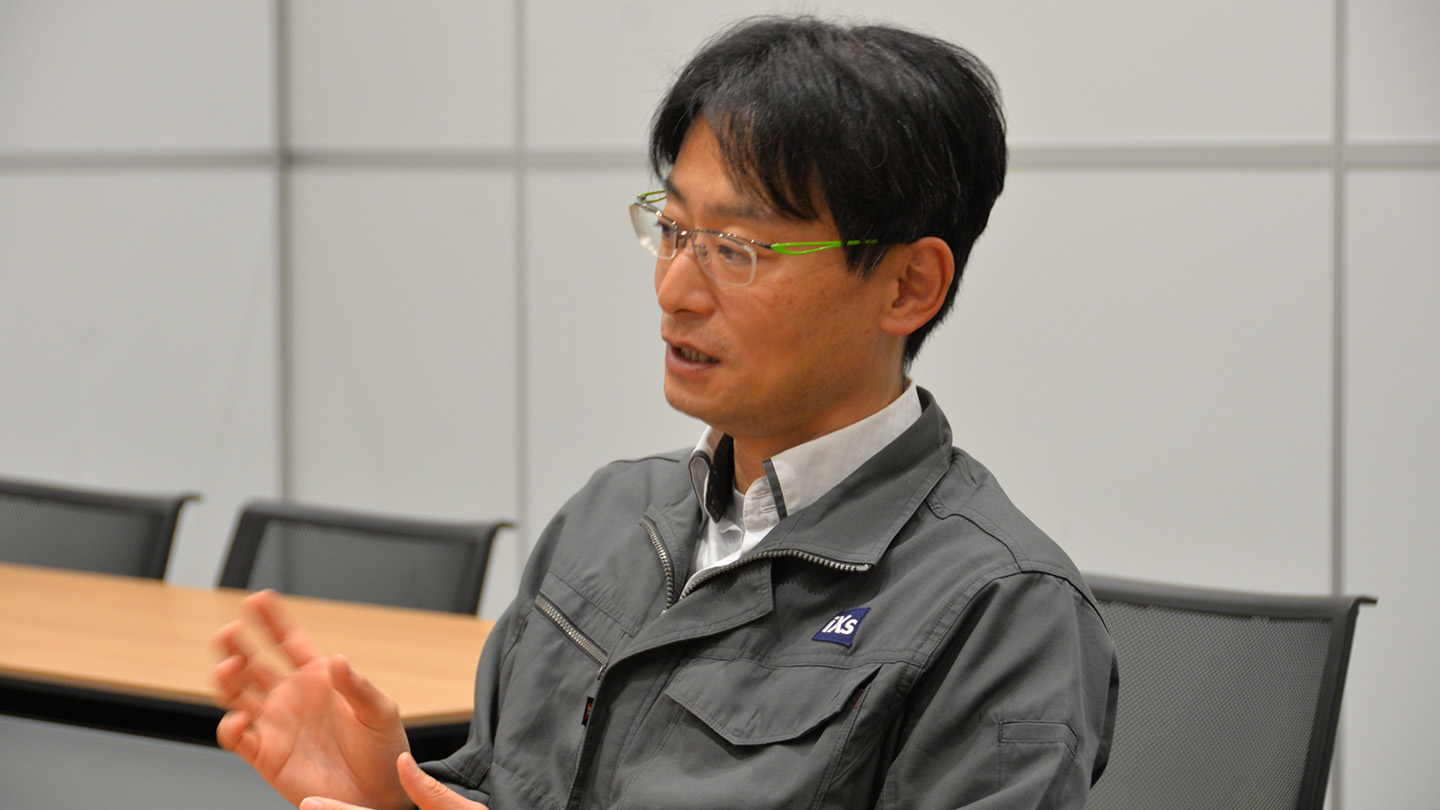
-イクシス社の強みについて教えてください。
アニメの影響からか、世間では「ロボット=完璧なもの」というイメージが持たれています。実際に先進的な技術を持ったロボットベンチャーの多くには優秀なエンジニアが在籍しており、誰もが驚くようなロボットが開発されています。
しかし、ロボットへの期待値が高すぎるあまり、現場でロボットが止まったり故障したりして誰もそれをフォローできない環境に陥ると「これじゃ使えないですよ」と返送されてしまうというシーンが繰り返されているんです。
お掃除ロボットを利用したことがある方は、ボタンを押したときのことを思い出してみてください。開始後すぐに子どもが散らかした服やおもちゃに引っかかったり、ケーブルに引っかかって乗り上げてしまったりと、まったく掃除が進まなくてイラッとした経験があると思います。
日本のロボット技術は、世界でも非常に高性能で高テクノロジーであることは明らかです。しかし「こんなにいいロボットがあるのに、なぜ売れないのか」を考えた時、それはロボットの機能が足りないからでも、社会実装されていないからでもなく、別の場所に要因があると気づきました。
例えば、お掃除ロボットに掃除を滞りなく遂行してもらうためにはどうすればいいのか?私はまず、ロボットが動きやすいように環境を整えました。加えてその状態を維持するよう子どもたちにもしつこく言い続けた結果、どうなったか。ロボット自体はアップデートせずとも、掃除をきちんと終えるようになったのです。
これはインフラの業界でも全く同じことが言えます。ロボットを利用する(受け取る)側の環境や意識をロボットに合わせてもらうことで、その技術力を最大限に活かすことができると考えています。
そこで弊社が重視しているのは、「お客様と一緒に課題を考えながら解決につながるロボットを開発する」というプロセスです。先進的な技術のみに依存せず、お客様の現場に足を運び環境とニーズをしっかりと把握することによって、ミニマムのテクノロジーで課題解決を実現する。これが弊社の強みだと考えています。
インフラの現場を支える2つのサービス
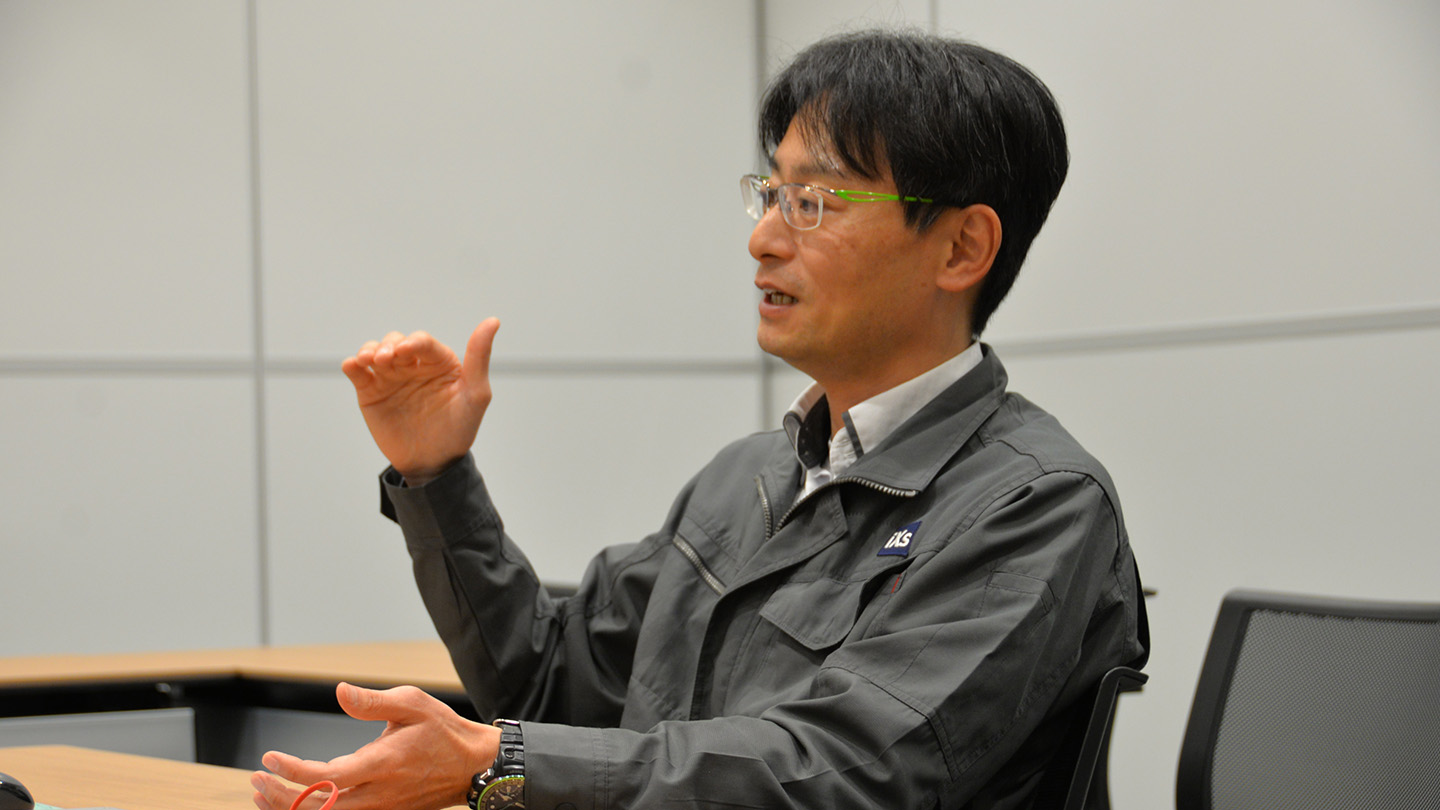
-具体的にはどのような製品やサービスを展開されていますか。
弊社では大きく2つの事業を展開しています。
まず1つ目は、ロボット開発です。簡単に説明すると、点検や検査を行うロボットを開発・提供しています。
プラントや工場のコピーをサイバー空間上に作り、そこにすべてのデータを記録してシミュレーションをすることで、ライフサイクルコストの削減が可能です。
代表的な製品に、i-Con Walker®という自動巡回システムがあります。これはBIM/CIMデータを元に走行用の地図を生成し、点検結果をBIM/CIMの属性情報に書き戻す、双方向のデータ連携機能を持ったデジタルツインを体現する巡回システムです。建設・鉄道業界のお客様と一緒に共同開発をして各業界に普及を進めております。
インフラ業界の現場には本当に熟練でプロフェッショナル意識の強い方が多いのですが、実はここが課題で、人手不足の今、誰が担当しても同じクオリティで現場作業を完遂できる仕組み作りを進めていく必要があります。
実際に現場を見に行った際、熟練の職人さんがデスクで一生懸命エクセル作業をやっている姿を見て驚きました。人手不足が叫ばれているはずなのに、なぜ現場ではなくエクセル作業に時間を割いているのかと。そのデスクワークの時間を現場作業に充てれば、コストは半分、売上は2倍になるでしょう。
そういう現場では、いきなり物理的なロボットは売り込まずタブレット一台から提案しています。最初からロボットですべてを自動化してしまうと、どうしても運用時に不具合が起きてしまうので、まずは簡単な作業を自動化するところから提案して効果を実感していただいた後に他のシステムを紹介するようにしています。
2つ目は、インフラに特化したAI、3Dソリューションです。
昨今、公共工事における入札では総合評価方式が採用されていて、価格の安さだけではなく企業の経営状態や新技術の投入などが大きな加点ポイントになっており、各企業がこぞって高性能な新技術を求めています。
そこでロボット×テクノロジーの技術を持つ弊社にも多くの企業から依頼があり、様々なシステムを開発。国土交通省の新技術情報提供システム「NETIS(New Technology Information System)」に登録しています。
一般的なロボットベンチャーやテックベンチャーだと、自社の持つ知識や技術を集めて最先端ロボットやシステムを完成させてから営業をかけるところ、弊社では企業のニーズに沿って一緒に技術を開発していくプロセスで取り組んでいます。ユニークなこの手法に評価をいただき、現在では全国に数千社の取引先があります。
弊社としてはまだ確実性が保証できないシステムを使っていただきフィードバックをもらえる点がありがたいですし、導入先の企業としてはまだ誰も知らない新しい技術を採用できる点がメリットになるため、Win-Winな仕組みだと思っています。
ロボット制作を続けたい――わずか1週間で学生起業家に
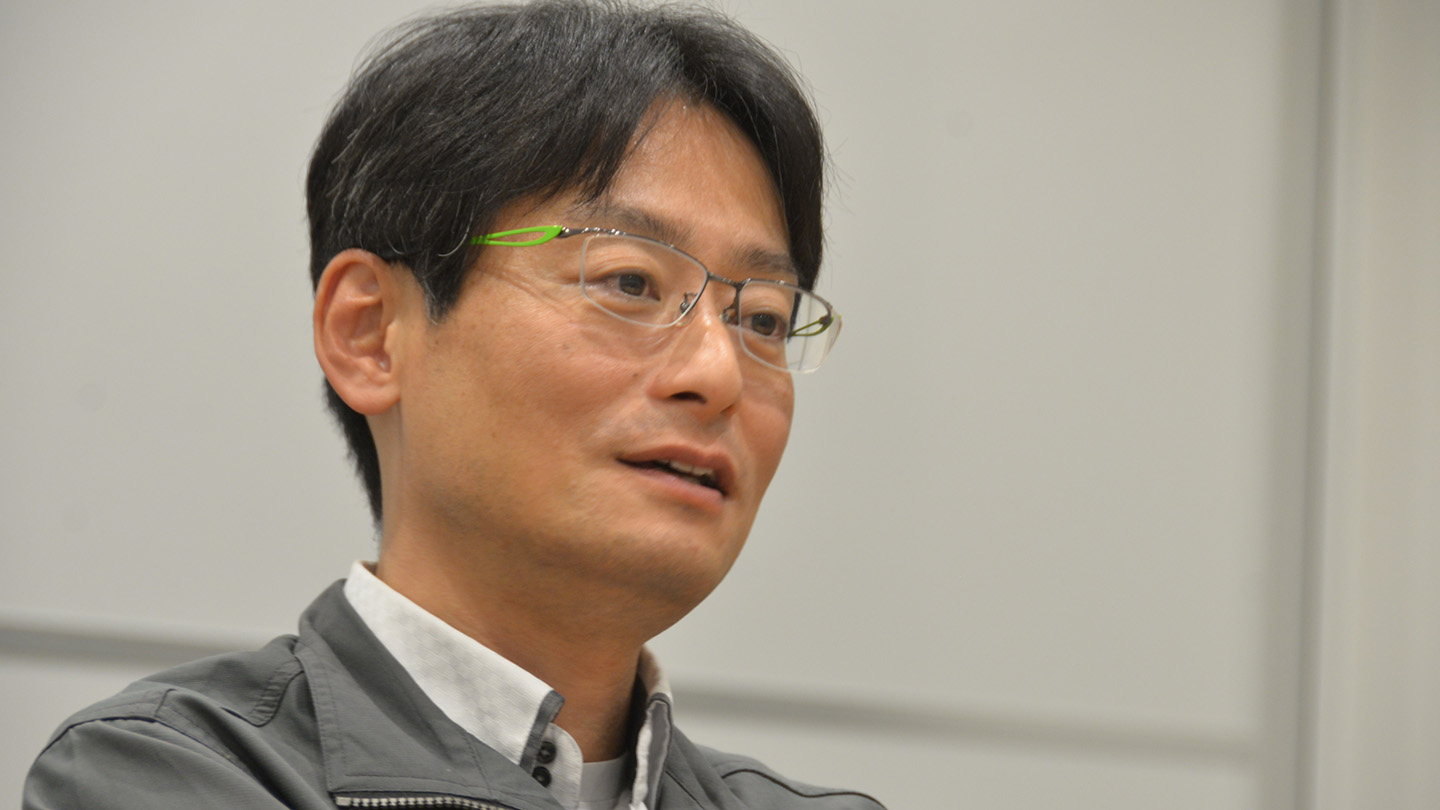
-創業当時から現在までの道のりを教えてください。
私の出身は山口県下松市です。非常にのどかな場所で、当時はテレビのチャンネルが4つしかなく、流行っていたアニメやロボットをほとんど知らずに育ちました。
一方で物心ついた頃からものづくりが大好きで、NHKのロボコンに出場したい一心で大学に進学。入学と同時にロボットサークルに入り、水を得た魚のごとく毎週のように秋葉原に通っていましたね。当時は相当なロボット少年だったと思います。
大学3年生の時には現・ソニーグループ株式会社 執行役 副社長CTOである北野さんが立ち上げたロボカップの世界大会に出場することになり、有志メンバーで精力的に活動していました。
ところが活動を続けるにあたって、資金が不足してしまい…。開発費に加えて大会の遠征費も必要なのですが、アルバイト代だけでは賄えず、かといって何度も親に頼る訳にもいかず途方に暮れていました。
そんな時、私たちが作ったロボットを売ってほしいという話をいただき、正式に売買するため会社を立ち上げました。駅前の本屋さんで“会社の作り方”という本を1冊買って、事業計画もないまま、1週間後にはもう起業していましたね。
-開発費や遠征費を稼ぐために会社を立ち上げられたのですね。
そうなんです。サークル活動の延長線上で立ち上げた会社なので、当初は大学院を卒業する際には誰かに譲るつもりでいました。ところが会社を立ち上げた後、仕事の依頼が何かしらと続いて、辞めるに辞められず(笑)。
時間稼ぎをかねて博士課程に進み「まだ学生です」と言いながら、しばらく経営を続けました。本当に“好き”の延長でやっていたのですが、タイミング良くロボットブームが起こったことも追い風だったのでしょうね。
しかし2005年の愛知万博が終わったタイミングで、華やかなロボットブームが去ってしまいました。ロボットは夢のある商品だと世間に認識してもらったけれど、やはりどこか現実的ではないということで、多くの企業が手を引いていきました。
-それでもあきらめずにロボットに関わり続けられた理由は何でしょうか。
この夢のあるロボットをどうやったら使ってもらえるか?と考えた時に思い浮かんだのが、レスキューロボットです。大地震が頻発している昨今ですが、当時は10年に一度と言われるほど珍しく、レスキューロボットは存在しているけれど活躍の場がない、そんな状況でした。
そうするとロボットはアップデートをする機会がなくトレーニングもしないため、人も環境も育ちません。福島原発事故の際、ロボットはあるのに1つも出動できなかったのですよ。
そこで“本当に役立つインフラに特化したロボットを作ろう”と決意しました。
ところが最初はかなり骨を折りました。インフラ業界は参入障壁が非常に高く、商談していると二言目には「実績はありますか?」と聞かれます。当時はもちろん実績がなかったので、一社ずつ試作品を作って提案して、実績を積んでいきました。
最初に提案したのが高速道路の企業だったのですが、試作品が一発で動いたことから高評価をいただき、そこから口コミが広がって一気に業績が伸びました。
インフラ業界全体を一緒に変えていける企業に出資していただきたい
-資金面でこれまで苦労された出来事や印象的な出来事はありますか?
資金調達を始めるまでは自己資金で経営を賄ってきたので、当初はとにかく資金面で苦労しました。
ただその中で運が良かったのは、神奈川県川崎市に本社を設置したことです。実は川崎市は中小企業支援やロボットに力を入れていて、次世代産業を担う技術者の育成を目的に市主催でロボコンを実施しているほどです。
ベンチャーだった弊社も川崎市に本社を構えるようになってから、展示会やイベントのお誘いで声をかけていただくようになりました。信用も実績もない中でここまで経営を続けてこられたのは、川崎市からのサポートがあったからこそです。
自治体との連携によって会社の信用度が高まるといったメリットがある一方、弊社の技術などを市に共有することで、良好な関係を築けていると思います。

-2022年にENEOSの出資を受けることになったときの心情や、実際に出資を受けてからの感想を教えてください。
弊社は創業当初から、常にその業界のトップ企業の課題を解決することを目指しています。そのため以前から、産業インフラ業界の第一線で活躍されているENEOSとはいつか共同開発したいという想いがありました。
また、弊社は企業の課題解決だけにとどまらず、業界全体を一緒に変えていける企業に出資していただきたいという想いがある中でENEOSにアプローチをしていたので、出資が決まった時は非常に嬉しかったです。
実際に出資を受けて、“業界を変えていこう”という前向きな話をできていることもありがたいですね。
-今後、取り組んでいきたい計画や目標はありますか?
まずは「ロボット×テクノロジーで社会を守る」というミッションを成し遂げるために、開発を進めながらどのように社会実装できるのかを同時進行で検討していきます。ENEOSとの共同開発においては、現場の製油所や次世代エネルギー系の現場の中ですぐに使えるサービスの開発を進めており、将来的には一緒に海外展開にも挑戦していきたいです。
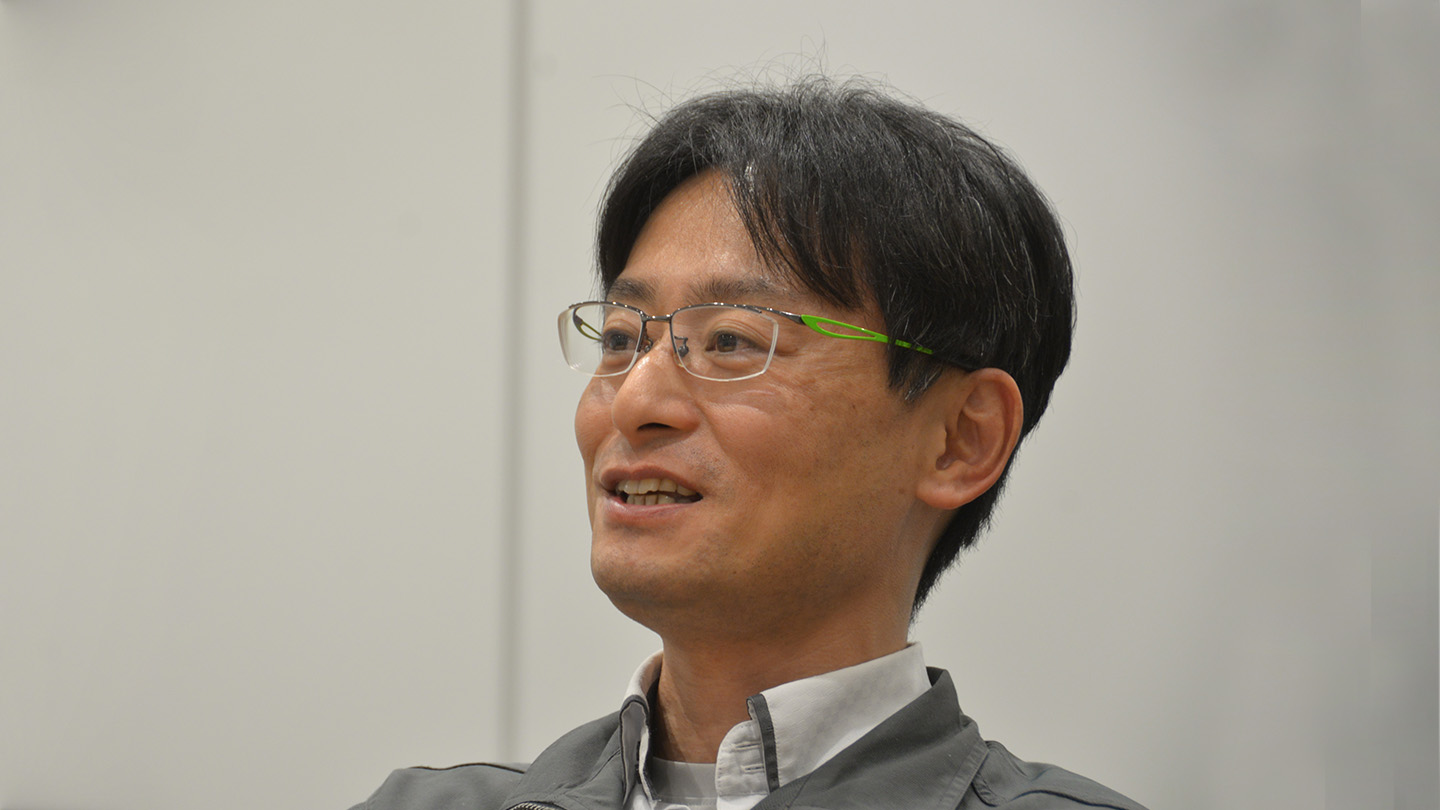
-最後に、今後ロボットをどのような存在にしていきたいですか?
一時のブームで注目を集めたロボットですが、私はいまだに“客寄せパンダ”的な存在で、見た目が可愛いことに注目が集まっていたり、万能なイメージを強く持たれていることを残念に感じています。ロボットは昨今の人手不足や建設物の老朽化、さらには働き方改革などに貢献する実用的な存在であり、効果的な運用が求められています。
ロボットを最大限に活用するためには、技術を追求した高性能ロボットの開発ではなく、ロボットを使う側の意識改革や環境整備が重要です。
“「人に代わるモノ」ではなく、「人の助けになるモノ」を創る”という信念のもと、弊社では実際に現場に足を運び、お客様と共通言語を話し、お客様と一緒に課題を見つけることから共同開発していくというプロセスで、これからも他にはない社会課題の解決を進めていきたいと考えています。